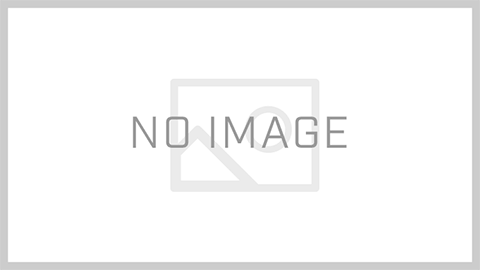こんにちは、木の実です。
フルタイム勤務の会社員を続けながら副業フリーランスに挑戦しています。
会社員として長く勤めていると、交友関係が職場の同僚に偏ってきちゃうことありませんか?
同僚と家族を除くと、つながっているのはたまにしか会わない学生時代の友人しかいない!なんてことも。
それでも少し前までは、職場の同僚と飲みに行く機会も多く、交友関係が狭いと感じることも少なかった…
それが、コロナ禍で人との付き合い方も変わり、さらに自分の立場が上がったことで後輩や部下は気軽に誘えなくなってしまった…
職場での人間関係の変化から、「会社以外にも人とのつながりが欲しい」「自分の居場所となるコミュニティを見つけたい」と感じる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、職場とは違うフラット関係性を築きやすい3つの関わり方のスタイルをご紹介します。「自分に合った場所」が見つかるヒントになれば嬉しいです。
気軽につながれるコミュニティスタイル3選

会社以外にも人とのつながりが欲しいと感じた時、「具体的にどこで探せば良いの?」「うまく馴染めなかったら嫌だな…」と、なかなか一歩を踏み出せない人も多いと思います。
でも、実は「新しい人間関係」といっても、最初から長く続けることを前提に考えなくても大丈夫。
最近では、1回だけ参加できるイベントや、ゆるく続く集まりも増えています。
まずは「お試しでいい」という感覚で、気軽に足を運びやすいコミュニティスタイルを3つご紹介します。
① 好きなことをきっかけに自然につながる
何か共通点があると人との距離は自然と縮まりやすくなりますよね。習い事や趣味の教室・推し活では、利害関係を意識せず「好きなこと」をきっかけに会話が始まります。
特に、月に1回や週に1回など、ゆるやかながらも定期的に顔を合わせるものなら、自分から意識して行動しなくても少しずつ関係が育っていきます。
職場では立場や年齢差を意識してしまう場面もありますが、趣味の場ではそれがほとんどありません。
私自身も、趣味で通っていたダンス、写真、和菓子作りといった教室で、年齢も仕事もバラバラながら、自然と会話が生まれ、食事に行く仲間もできました。
どの習い事でも「好きなことが同じ」という接点があったため、立場や肩書きを超えて話せる関係が生まれたのだと思います。
- 共通の「好きなこと」が自然な会話のきっかけに
- 継続的に顔を合わせることで無理なく関係ができる
- 年齢や職業に関係なくフラットな関係を築きやすい
② 学びを通じて目標に向かって並走する
勉強会やキャリア系のワークショップなど「学び」を共有する場も、年齢・職業関係なくフラットな関係を築ける場のひとつです。特定の資格取得のための対策講座などもありますね。
こうした場では、全員が「学び手」。一緒に「頑張る仲間」として対等な立場で関われます。
年齢や職場での立場なんて気にすることなく、目標に向かって並走する感覚があるので、やがて「戦友」のような関係性になることも少なくありません。
話す内容も自然と「目標」や「学び」につながるため、雑談や自己開示が苦手な人でも入りやすい特徴があります。
- 「学び」を通じて並走することで「戦友」のような関係性に
- 年齢・立場に縛られず対等な関係が築きやすい
- 話題があらかじめ設定されているため安心感がある
③ 会話が苦手でもゆるく参加できる
話すことに自信がない、もしくはあまり積極的に会話をしたくない場合でも、つながりを感じられる場があります。
それが、作業会やもくもく会と呼ばれる形式の集まりです。
ここでは、参加者それぞれが自分の作業に集中しつつ、時折、作業の合間に雑談を交わす程度。会話が前提ではないため、気を使わずに参加しやすいのが特徴です。
仕事の副業作業、資格の勉強、趣味の創作活動など、目的は人それぞれですが、同じ時間を静かに共有するだけでも、ほどよい連帯感が生まれます。
- 会話が前提ではないため、気楽に参加できる
- 「何かをする時間を共有」することで自然と連帯感が生まれる
- 参加ハードルが低く、初めてでもなじみやすい
好きなこと、学びたいこと、手を動かすこと
どんなきっかけでも、自然に人とつながる方法は意外とたくさんあります。
自分に合ったコミュニティ どこで見つける?
「自分に合いそうな関わり方はわかったけれど、具体的にどこで見つけるの?」
そう思った方に向けて、ここでは、コミュニティを探す具体的な方法と、参加する時のハードルを下げるコツを紹介します。
コミュニティの探し方
◆ イベント検索サイトで探す
Peatixやこくちーずなどのイベント検索プラットフォームを活用すると、自分に合うコミュニティを効率よく探せます。
▷ 主なサイト
▷ 検索のコツ
「習い事」「作業会」「朝活」「読書会」「勉強会」など、参加スタイルをイメージしながらキーワード検索する
◆ SNSや個人発信から探す
今は、SNSやnote、Voicyなどの発信者をきっかけに、コミュニティが派生するケースも増えています。
▷ 探し方の例
- Instagram:ダイレクトに教室情報を発信しているアカウントも多い
- X(旧Twitter):「#朝活」「#作業会」などのタグの発信をチェック
- note:習い事、副業、趣味テーマで検索し、コミュニティ情報を発信している個人やグループを探す
- Voicy:パーソナリティが開くリスナーコミュニティやイベントを活用する
◆ 地域の習い事・カルチャースクールを活用する
リアルでのつながりを求めるなら、地域の習い事教室やカルチャースクールも有力な選択肢です。
▷ 具体例
- 大手カルチャーセンター(NHK、読売、朝日など)
- 公民館・市民センター主催の講座(料理・手芸・英会話など)
最初の一歩を踏み出すコツ
行きたい場所が見つかっても、「最初の一歩」が怖いと感じることはよくあります。ここでは、気軽に試すためのちょっとしたコツをご紹介します。
▷ 主催者がいる場を選ぶ
自分が主導する必要がなく、進行や話題を作ってもらえるため、参加者として気楽に入れます。
習い事、ワークショップなど、主催者主導型のイベントがおすすめです。
▷ テーマが決まっている場を選ぶ
読書会、もくもく作業会など、活動内容があらかじめ決まっている場もおすすめです。
雑談が苦手な人でも、テーマに集中して参加できるため安心感があります。
▷ まずは「一回だけ」行ってみる
最初から「続けなければ」「馴染まなければ」と思う必要はありません。
「1回だけ試してみる」という軽い気持ちで参加すれば、心理的なハードルがぐっと下がります。
昔と違い、「倶楽部に所属する」「サークルに入会する」といった「籍をおく」という手続きをせずとも、「お試し」感覚で参加できるコミュニティも少なくありません。
合わなかったら、次を探せばいいだけ。「あ、ここは違った」と、ひとつ選択肢を減らせたと捉えて、どんどん次の候補に進んでOKです。
コミュニティ探しに正解・不正解はありません。実際に自分に合うかどうかは試してみないとわからないもの。まずは気になった場所に参加してみることで、職場以外の居場所を見つける一歩になります。
今日、5分だけ時間をとって、「趣味」「勉強会」「作業会」など、
気になるワードを検索してみるー
そして、ひとつ「試しに」予定に入れてみるー
そんな小さな一歩から、会社とは違うコミュニティ探しは始まります。
最後に
近年、働き方や人間関係のあり方は大きく変化しています。
リモートワークや副業の普及により、会社内のつながりが希薄になったと感じる人は増えました。また、ハラスメントへのリスクヘッジから、部下や同僚と気軽に話すことが難しいと感じる場面も少なくありません。
こうした背景から、職場とは別に、利害関係のないフラットな人間関係を持つことの重要性が高まっています。
今は、仮想空間でつながることもできれば、困ったときにChatGPTなどのAIに相談することもできる時代です。実際、こうしたツールの普及により、気軽にアドバイスや答えを探しす手段は以前よりも格段に増えました。
しかし、実在する「生きた人」と言葉を交わせるつながりは、今も変わらず大切です。オンラインであっても、相手の存在を感じながら関わることに、リアルな安心感があります。
こうしたリアルなつながりを少しずつ開拓していくことは、会社の人間関係だけに依存しない、生き方や働き方を支える土台になります。
さっそく今日から、自分に合いそうなコミュニティ探しを始めてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
木の実
-3.jpg)


-2-320x180.jpg)

-3-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
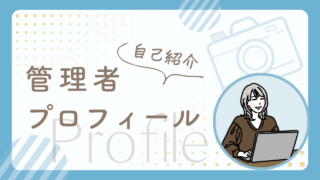
-1-320x180.jpg)